
|

|
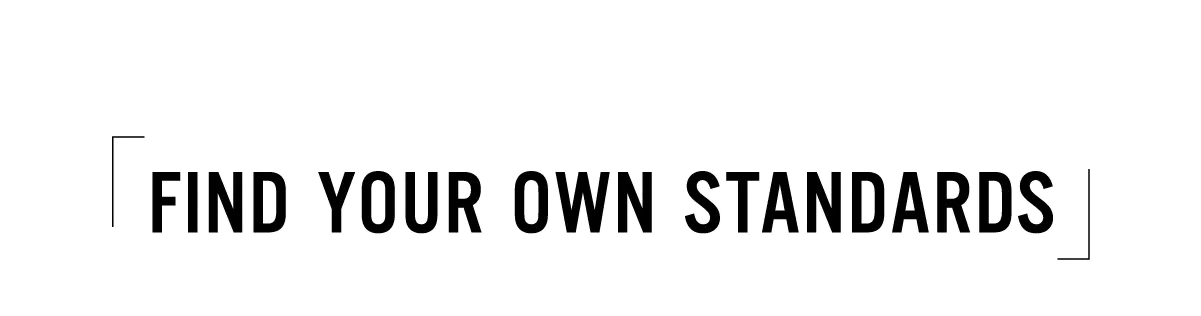
UNCOLORED WEEKLY MAGAZINEは、クラフトカルチャーを軸に、世界中を独自取材し、次の時代のヒントを見つける為のカルチャーマガジンです。
|

|
|
Hello Everyone. 先日頂いた桃がとても美味しくて、止まらなくなってます。気付くと無くなるまで食べちゃうので、この時期 "桃" には注意です! 今週のメルマガ、スタートです。 |

|

|

|

|
|
BLUE SIXの「KETO MIX NUTS」 抽選で20名様へプレゼント! |
|
長く健康な身体でいる。これは永遠のテーマでもあります。 「身体は食べた物で出来ている」からこそ、いつ何を食べるのか? が、とても重要になります。 生活していて困るのが、外出時の捕食。どうしても炭水化物に偏ってしまい、糖質過多になってしまいがちです。 外出時の空腹時に、急激な血糖値上昇を抑え、良質な油を補給する。 そんな“ケトジェニック”的発想から生まれたのが、BLUE SIXの「KETO MIX NUTS」です。 まずは気軽にお試しください! プレゼントの応募締め切り:2025年8月14日(木) |

|
| 「Brown豊洲店、はじまりの日。」 |
|
東京・豊洲に、ワンコのようちえん「Brown」の2号店が誕生しました。 中目黒で15年。たくさんのワンコや人々との出会いを重ねてきたBrownが、新しい土地で、新しい一歩を踏み出しました。 |

|
|
ワンコは、生後3カ月を過ぎた頃から、パピートレーニングが始まります。 この時期に身につける社会性は、ワンコの一生にとって、とても大切なもの。 幼少期を逃すと、大人になってから、吠えや飛びつき、噛みつきなど問題行動が多くなるケースがあるからです。 |

|
|
ようちえんでは、担当トレーナーが基本的な指示やトリックのトレーニングを行います。パピー犬は他のワンコたちと過ごす時間を通して、人やワンコとの関わり方を学んでいきます。 ワンコだけでなく、飼い主も “犬という動物" について学んでいくことが、ワンコとの長い生活を楽しめる、唯一の方法だと考えています。 |

|
|
空間設計を手がけたのは、LINE-INC.代表の勝田隆夫さん。Brown豊洲店の空間づくりについて、お話しを伺いました。 「オーナーの安達さんからは、“作り込みすぎず、華美にせず、風が通るような開放的な空間に”というオーダーをいただきました。そこで、過ごしやすさと機能性のバランスを追求しました」 ドッグラン、ペットサロン、ショップ、ホテル。4つの機能を1つの空間に収め、すべての動線がシンプルになるように設計されています。 エントランスは一つに集約し、利用者もワンコたちも迷わない、心地よい回遊動線です。 また、空間構成の主役となるのは、天井高3.5mの広々としたドッグラン。大きなガラス窓からやわらかい自然光が差し込みます。 |

|

|
|
素材は、塗装壁、木目の床材、表情のあるレンガタイルなど、シンプルで手触り感のあるものが選ばれ、空間自体が静かな安心感を生み出しています。 ドッグランには滑りにくく足腰にやさしいクッションフロアを使用。ホテルスペースは24時間換気と個別空調を完備しています。 |

|
|
「風が通り抜ける、やさしい複合空間。それが、Brown豊洲店のコンセプトです」 そう語る勝田さんの声にも、やわらかな風が流れていました。 空間に“やさしさ”を設計するということ。 それは、過ごしやすさ、心地よさ、そして信頼できる場を作ること。 広々としたドッグランでは、今日も、風が通り抜けています。 Brown 豊洲店 東京都江東区豊洲2-1-9 豊洲セイルパーク B棟内 |
|

|
| 「GPT-5 はどこまで出来るのか?」 |
|
Tate「GPT-5が出たけど、正直、何ができるようになるの?」 Luna「今までと違うのは、“反応”じゃなくて、“先回り”してくるところかも。」 Tate「先回り?」 Luna「言われたことに答えるだけじゃなくて、“これが必要になるだろうな”って、先に出してくる感じ。」 Tate「たとえば、社内の業務で言うと、どんなイメージなの?」 Luna「事務スタッフの業務なら、会議を録音して、発言をまとめて、次に誰が何をやるかまで整理して、その人の予定に合わせてリマインドまで入れる。そんなレベル。」 Tate「……もう人じゃなくても回るね、それ。」 Luna「業務自体はね。でも、“誰がやるか”に意味があることもまだあるから。」 |

|
|
Tate「じゃあ僕の仕事だったらどう? 初対面の人と話すとき、過去の発言とかプロフィールとかまとめといてって言ったら?」 Luna「できると思う。それどころか、“この人にはこう切り出した方がいい”っていう提案も出せるかもしれない。」 Tate「……まじか。じゃあ“どこで会うのがいいか”も決めてもらえる?」 Luna「たぶんね。相手の性格や過去の傾向から、“話が通りやすい環境”まで含めて提案してくる可能性がある。」 Tate「それ、俺が考えることなくなってくるな……」 |

|
|
Luna「でも、考えないんじゃなくて、“考える地点”が変わるだけだと思う。」 Tate「つまり、“始める前の準備”はもうAIがやってくれて、人間は“何を選ぶか”に集中できるってこと?」 Luna「そう。“始め方”まで整うから、余計な迷いが減る。」 Tate「それ、めちゃくちゃ楽になるけど、ちょっと怖くもあるな。」 Luna「“何を任せて、何をやるか”は、ちゃんと自分で決めないとね。それがないと、全部流れていく。」 Tate「GPT-5、と言うか、AIが良いか悪いかは……使う人次第なんだろうね。」 |

|
| 「基本ができていない組織は、伸びない」 |
|
組織が崩れる理由は、外からの攻撃もあれば、中からじわじわ壊れていくこともある。 スキルでも、ビジョンでもない。 基本的なことが、ちゃんとできているか。 それだけで、組織の未来は大きく変わる。 まず、お金。 どこから入って、どこに出ていくのか。 その流れが、ちゃんと“見える”ようになっているか。 これは組織の血液みたいなもので、 どこかに詰まりがあると、そこから腐っていく。 やりたいこと、始めたいこと、全部にお金は関わる。 「回っている感じがする」ではダメで、 入り口と出口が、オープンであること。 それが“きれいな血液”を流す条件である。 次に、人。 2人以上集まれば、マネジメントは必要になる。 目的を共有するだけでなく、 どうやって動くかという“ルール”が必要になる。 ここがあいまいな組織は、必ず崩れる。 人によってルールが変わる。 その日によって判断が変わる。 一部の人しか情報を持っていない。 問題が起きても、上には届かない。 そんな組織は、外から見えなくても、内側から崩れていく。 「良いことだけを報告する」 「悪いことは下で処理する」 「忙しそうだから、今は言わない」 そういう“静かな判断”の積み重ねが、組織全体を濁らせていく。 だからこそ必要なのは、 情報とお金の透明性。 人任せにしない倫理観。 そして、明文化された、公平性のあるルール。 組織を維持するのは簡単ではないが、 “発展させる”のは、別の次元の話だ。 スピードが出てきたとき、メンバーが増えたとき、 “基本ができていない組織”は、成長の途中で割れていく。 華やかなビジョンより、 静かな基礎の方が、組織を救うことがある。 |

|
|
8月のテーマは「筋肉」。 BLUE SIXは、テニスのトッププロ選手が練習やトレーニングを行う施設「BLUE SIX TRAINING CLUB」を運営しています。 今月は、スポーツ選手にとっての「筋肉」について取り上げます。 |

|
|
技術×筋肉=パフォーマンス スポーツ選手は、テクニックだけで勝負しているわけではありません。 どの競技でもプラスアルファのトレーニングが必須です。 テニスでは、1日2〜4時間のオンコート練習に加えて、1〜2時間程度のトレーニングを行います。 内容は、走り込み、フットワーク、ウエイトトレーニングなど。ウエイトでは、背中・胸・足・お尻など、威力のあるボールを打つために欠かせない筋肉を主に鍛えます。 目的は筋肉を大きくすることではなく、瞬発力・力の爆発力を高めること。 特にテニスでは、ボールを打ってから相手に届くまで約2秒。 サーブリターンでは、わずか1秒で反応しなければなりません。 その一瞬に必要なのは、最大限のパワーとスピードです。 |

|
|
プロトレーナーに聞く「筋肉の本質」 テニス、バスケットボール、野球、アメフトのプロ選手を国内外でサポートする専属トレーナーに話を聞きました。 どの競技にも共通する大切なことは「まず身体のベースを作ること」。 競技ごとに使う筋肉は異なっても、土台となる筋力がなければ競技力は伸びません。 そのうえで、競技特性に合ったトレーニングを追加していきます。 ・横の動きや切り返しは多くの競技で共通 ・アメフトのように体格のよさが求められる競技もある ・ベンチプレスやスクワットなどの基本的なトレーニングはどの競技にも重要 一流選手ほど、技術以前に「身体づくり」に時間とエネルギーをかけています。 |

|
|
日本人選手と外国人選手の差とは 「外国人選手は身体が大きい」と感じたことはありませんか? もちろん遺伝や体格の差もありますが、もうひとつの違いが“ウエイトトレーニングへの意識”です。 彼らは日常的にウエイトトレーニングを行い、試合後も自らを追い込み鍛えます。 一方、日本では技術練習が優先され、ウエイトトレーニングが軽視される傾向も。 その意識の差が“身体能力の差”に現れているのかもしれませんね。 スポーツ選手にとって筋肉は、競技で戦うための土台。 そしてその土台と真剣に向き合い、鍛え続ける日々の積み重ねが、大きなパフォーマンスを生み出しています。 その姿勢に、私たちの毎日の健康づくりのヒントがあるかもしれません。 Find your own standards. |

|

|
|
オーナー安達に聞いてみたい事を大募集!いただいた質問はメールマガジン内でお答えします。
全ての質問に答えられない場合もございますが、翌週以降で回答することもありますので、どしどしと、好きな事を質問して下さい! info@un-colored.com |

こんにちは。
中小企業を経営して8年目になる40代の男性です。 初めての質問なのですが、社内ミーティングについての相談があります。 どうしても場が盛り上がらず、発言も少ない状態が続いています。 形式的に集まってはいるのですが、意味のある時間になっていないような感覚があります。 こういった場合、何から見直すべきでしょうか? 

うちの場合、ミーティングは“会話の場”ではなく、解決のための場として機能しています。
各ブランドの責任者が、自分の数字と状況を整理し、課題を自分の言葉で出す。 そこに対して、解決策を持ち寄るというのが基本の流れです。 でも、現場が気づいていない課題や、全体を見ていてこそ分かるボトルネックもある。 そういう時は、僕の方から課題と解決策をセットで渡すこともあります。 「考える」よりも、「動かす」ことを優先する場面もある。 それが今、必要だと感じれば、遠慮せずに介入します。 だからまず大事なのは、 ミーティングの目的が参加者に明確かどうか。 “何を決めるためにここにいるのか” が分かっていないと、会議は止まります。 次に、参加者に役割と責任があるかどうか。 発言しない=責任を持っていない、というサインでもあります。 場に立っている以上は、自分の視点で動く責任があると思っています。 感情や温度感ではなく、 数字→課題→解決という流れをベースにしていくと、 話が具体的になって、場が“前に進む場”になります。 ミーティングが盛り上がるかどうかより、動いているかどうか。 それを意識しています。 
|

安達さん、こんにちは。
毎週メールマガジンを楽しみにしています。 私は現在会社員として働いている30代の女性です。 将来、飲食店を持ちたいという夢があり、いまは少しずつですが貯金をしています。 でも、最近いろんなお店がすぐに閉店したり、話題になっても長続きしなかったりするのを見て、 「本当にやっていけるのかな」と不安に思うようになりました。 飲食業界は流行も早く、競争も激しいと思います。 どうすれば、長く続けられるお店をつくれるのでしょうか? 

「リスクを取って挑戦する」という言葉は、かっこいい響きがあります。
でも僕は、その “リスクの取り方”にこそ、大事な判断基準がある、と思っています。 会社員からいきなり飲食店を始めるというのは、挑戦ではなく、賭けに近いかもしれません。 それも、自分のこれまでの経験とあまりにも遠い場所にいきなり飛び込む賭け。 そういう賭けは、たいてい負けます。 だから、僕がアドバイスするとすれば、 まずは、業績を伸ばしている飲食系の会社に転職してみること。 現場に入って、数字を見る、動きを学ぶ、人と出会う。 そこで得られるノウハウと人脈は、お金を貯めることよりもずっと大きな資産になります。 もうひとつ大切なのは、「なぜ自分はお店をやりたいのか」を、 言葉にできるまでとことん突き詰めること。 料理が好きだから?独立したいから?自由になりたいから? その動機の深さと具体性が、そのままお店の持続力になると思います。 やりたい事は、現実から遠ざけない方が、実現しやすいと思います。 一歩ずつ近づきながら、冷静に、でも目標への足は止めずに。 
|


僕の好きな写真です。
撮った時よりも、後から印刷し、見てからの方が好きになりました。 優しさがあって、自由があって、自然の良さを感じます。 Have a good weekend!! 
|

|






